※本記事は獣医師による監修を受けておりません。飼い主としての経験と一般的に信頼性の高い情報に基づいて執筆しています。個別の体調や食行動に関しては、必要に応じて動物病院にご相談ください。
【犬の味覚を解説】犬は食べ物の味がわかる?味覚・嗅覚・食べ好みの秘密とは
「うちの子、このおやつは食べないのに、あれは大好き!」そんな食べ好みを見せる犬を見て、「犬って味がわかるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
今回は、犬の味覚や嗅覚、そして食べ好みの理由について、飼い主が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。愛犬との食生活をもっと豊かにするために、ぜひ最後までお読みください。
犬の味覚は人間とどう違う?味はわかっているの?
犬も人間と同じく、舌に「味蕾(みらい)」と呼ばれる味を感じる器官があります。ただし数が異なり、人間が約9,000個あるのに対して、犬は約1,700個と大きな差があります。
つまり、人間ほど繊細には味を感じ取れないということです。
犬が感じられる味の種類
- 甘味(特に母乳の糖分など)
- 酸味
- 苦味(本能的に避ける)
- 塩味(弱い感知力)
- うま味(肉由来のうまみ成分に反応)
犬は甘味やうま味を好む傾向があり、特に動物性タンパク質の味(うま味成分)には強く反応します。一方、苦味には本能的に警戒し、避けることが多いです。
犬の食欲を左右するのは「嗅覚」だった!?
犬の嗅覚は人間の100万倍以上とも言われ、味覚よりもにおいで食べ物を判断する傾向があります。
そのため、香りが強いフードやおやつに対して「おいしそう!」と感じやすいのです。
嗅覚が関係する「食べムラ」の例
- 袋を開けたてのドッグフードは食べるが、時間が経つと食べない
- 温めたごはんには喜んで飛びつく
- 同じおやつでも新しいものはよく食べる
これらは「味が変わった」のではなく、香りが弱まったことによる反応なのです。
犬が食べ好みをする理由
- 過去の成功体験
おいしいと感じたものを覚えていて、同じ味・香りに反応する。 - 学習行動
嫌な経験(薬を混ぜられたなど)を覚えていて避ける。 - 加齢や体調の変化
年齢や病気によって嗅覚や味覚が鈍くなり、食べムラが出ることも。
飼い主ができる工夫|食べ好みを防ぐ方法
- ドッグフードを温める
香りが立ち、食欲を刺激しやすくなります。 - 数種類のフードをローテーション
飽き防止&栄養の偏り防止にもなります。 - しっかり密封保存
酸化や湿気を防いで風味を保ちましょう。 - 与えすぎない
おやつや人間の食べ物をあげすぎるとフードを嫌がる原因に。
「味がわかる」=「おいしいと思っている」とは限らない
犬は人間と同じように「味がわかる」わけではありません。
香りや食感、温度、飼い主の反応など総合的な印象で「食べたいかどうか」を判断しています。
まとめ|犬の味覚を理解して、もっとおいしい食事時間を
犬にも味覚はありますが、食べ物を選ぶときにはにおいが大きな役割を果たしています。
「この子、好き嫌いが激しいな」と思ったときには、香りや温度、保存方法を見直してみると、また食べてくれることがあります。
愛犬が楽しく食事できるよう、ちょっとした工夫と観察を日々のごはんに取り入れてみてくださいね。

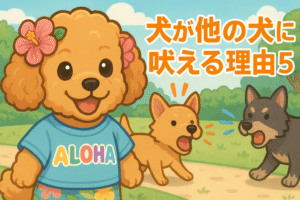




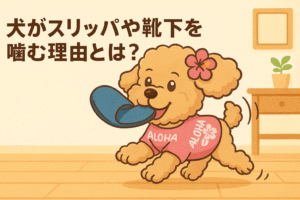


コメント